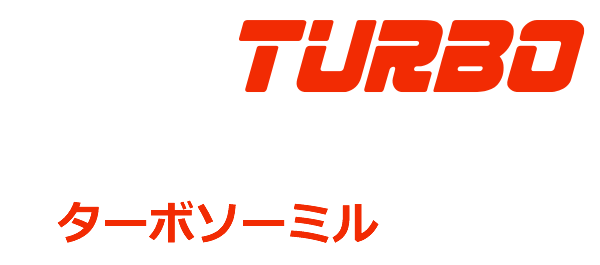どこでも運べる丸鋸式簡易製材機デモンストレーション@北海道中川町

2025年2月22日(土) と23日(日)に、ターボソーミル簡易製材機【ウォリアー M6-13M】のデモンストレーションを北海道中川町にて行いました。
また、デモ開催日が「きこり祭」と重なったので、イベントにも参加してきました!
思い出の場所・北海道中川町
中川町で例年行われているイベント「きこり祭」の開催に併せて、林業・木工・建築関係の方々が集まるということでお声がけいただき、デモンストレーション開催が決まりました。
中川町とのお付き合いは、以前青森県の林業職だった頃、研修で伺った2016年に遡ります。
同町では、林業を核とした地域づくりを行っており、川上から川下まで一貫して様々な施策に取り組んでいます。
中でも一本の木の価値に最大限付加価値をつけるために木工や樹皮細工などの商品づくりやブランディングなどを実施しており、量ではなく質の林業を実践していて、個人的には同町での研修での学びが林業へ対する考えの転換点となりました。

その研修は11月だったのですが、町の担当者の方から、「2月にきこり祭りがあるけれど参加しないか」と誘っていただき、とても楽しそうな大会だったので、その場で出場を約束し、第3回大会に出場させていただきました。その後も第4~5回大会にも参加しています。
コロナがあってからは参加できていなかったのですが、今回は記念すべき10回大会ということで、参加のお声がけをいただき、6年振りの訪問となりました。
久々にお会いできる方々を思うと、準備作業もとても捗りました。
分解して持ち運べる簡易製材機
今回のデモ会場は、北海道!
事務所のある青森県からは、フェリー+車での移動です。
ターボソーミルの簡易製材機は、分解することができるので、バンやトラックにも車載できます。
今回はハイエースの荷台とキャリーに積んで、北海道へ出発です!




ハイエースなら、設営や製材に必要な道具も一気に積み込めました。
写真を見ていただいてわかると思いますが、ターボソーミルは分解するととてもコンパクトなので、家族5人が乗り冬期4泊分の荷物を積んでも、まだ余裕がありました!
はじめまして!刃が90度角度をかえる簡易製材機です
今回のデモ機
ターボソーミル簡易製材機【ウォリアー M6-13M】
最も軽量で、コンパクトに分解・運搬できるモデルです。

極寒の中、簡易製材機の組み立て
デモ当日の朝は、マイナス17℃!
組み立てに要した時間は、役場職員の方や地域の方にもお手伝いいただき、お話しながら約2時間。
寒さにかじかむはずの手も、興奮からかあまり寒さを感じず作業が進みました。

デモンストレーション1日目
2月22日午後からデモンストレーションを行いました。
天候もよく、多くのお客様にお越しいただきました。

デモ用に用意してもらった木材はミズナラ。
普段青森で製材しているは、軟らかいスギ材だったので、硬いミズナラ&凍れてより一層硬化してる?!うまく切断できるかな…。
しかも試運転しそびれてしまい、一発本番という状況…!
恐る恐る刃を進めましたが、製材の断面はとても平滑で、いつも通りの製材を
することができました!

何度か往復し最初の断面が現れると、早速ご質問が飛び交いました!

・製材品の最大寸法は?
・刃のメンテナンス方法は?
・丸太の固定方法は?
などなど…
刃が90°角度を変えるスイングブレード製材機は、多くの方がご存知の帯鋸製材機とは、木取りや製材手順など異なる点が多く、イメージしにくい部分が多いと思いますが、実際に目の前で製材を見ていただくことで、ターボソーミルの革新性をお伝えすることができたと思います。
弊社でこれまで使用してきた帯鋸式製材機との比較や、それぞれのメリット・デメリットを説明させていただきながら、デモ会はあっという間に終了となりました。

デモンストレーション2日目
2月23日 きこり祭当日。
開会式前に時間をいただき、この日もデモンストレーション!

ターボソーミルの製材品を多くの方に見ていただき、興味を持ってくださいました。

ご来場者の中には、製材所を経営していた方も。
帯鋸式との違いやターボソーミル製材機の得意分野、活用方法や歩留まりを上げるための改善点など、貴重なご意見を伺うことができました。
同業種の方から「ターボソーミル製材機はおもしろい仕組みだよ!」と言っていただけたのが、少し自信になりました。

第10回きこり祭にも参加しました

丸太レース[きこりの部]に参戦!
きこり祭 丸太レースとは?
メインイベントは「丸太レース」。
道内外から多くの人が参加されていて、今年は合計35組がエントリーしていました。
「一般女子の部」「一般男子の部」「きこりの部」と分かれていて、「一般の部」はロープをかけた丸太を3人でゴールまで引っ張ります。
「きこりの部」は、昔の林業用道具を使用して雪上で丸太を運ぶ速さを競います。

弊社からは代表が参加!
以前参加した時のチームを再結成しました。
…ふんどし王子?

丸太レースの様子
レース中は、3種類(ガンタ・トビ・バチ)の道具で3つの技法を再現して、300〜400kgの丸太を移動させていきます。
2人がガンタで丸太を左右から挟み、1人が末口から押すのが基本形です。前方2人が丸太を引き上げ、後方の1人がタイミングを合わせて押します。

ガンタ(木回し)
:主に木を転がす(回す)ために使う道具。
両側から丸太を挟み持ち上げたり、傾斜地をバチで滑り降りる時のブレーキ代わりに使われたり、木口にかけて方で押すために使われた。
現在も、かかり木(倒した木が立木に引っかかって倒れなくなった状態)処理に使われることがある。
2人がトビを地面と丸太の間に差し込み、てこの原理でずらします。残る1人は、ガンタで丸太が転がらないように固定するのが基本形です。
トビ(鳶口)
:主に木口に刃先を引っかけて丸太を引っ張る道具。
てこの原理を応用し、大木を少しずつずらす場合などにも使われた。
ガンタと共に「藪出し:林内に散在している丸太を山土場へ引き出す作業」を行い、藪出し組のリーダーは鳶長と呼ばれ、木こりたちの憧れの的であったとかなかったとか。
丸太をバチに乗せ、縄で結えて引っ張ります。
1人が引っ張り、2人がガンタで押すのが基本形です。

バチ(人力バチ)
:「藪出し」によって集められた丸太を、急傾斜を下って平地まで下ろすための道具。
山男の中でも特に命知らずがバチの先頭に座り操作を行った。
暖傾斜では、1人が引っ張り、2人がガンタで押すなどして、馬が引ける山土場まで移動していた。山土場からは、「バチバチ」と呼ばれる馬用で丸太を運搬したという。
「第10回きこり祭 KIKORI丸太レース ルール説明」より引用
このように「きこりの部」は、現在はほとんど使用されることがない林業道具で昔の林業体験ができます。
参加者には95歳のベテラン林業家もいらっしゃって、巧みな技で丸太をバチに乗せる様子をみることができました。
協賛企業として
イベントに協賛させていただき、各賞受賞者へ賞品を贈呈させてもらいました。

スペシャルゲスト・大江裕さん
演歌歌手の大江裕さんが撮影できこり祭を訪れており、ステージでの歌唱の他、スペシャルゲストとして丸太レースに参戦、3位入賞と大活躍されていました!

中川町きこり祭での撮影は、3月22日(土)午後 HBC「大江裕の北海道 湯るり旅」で放送予定だそうです。

充実のマーケットブース
レース会場の隣には飲食・販売・体験ブースがあり、魅力的な出店者さんばかりで大盛況でした!

(開会前の混雑していない時間帯に撮影)

他にもキッズそり滑りコーナーや林業重機の展示など、たくさんの来場者で賑わっていました!
イベント終了!そして再び分解…
きこり祭の閉会式も無事終了し、私たちは製材機の撤収作業。

参加者の皆さんが手を貸してくださり、分解作業がサクサク進みました。
分解前は「この製材機が、本当にこの車に入るの?」「どうやって分解するの?」とのお声がいっぱいでした。
作業しながら説明し、実際に車載すると「へぇ〜。」と納得いただけた様子。
本当にびっくりするくらいコンパクトになります。
分解に要した時間は、1人での作業だと2時間程度でしたが、2〜3人だと1時間程度でできました。
2日間各1時間程度のデモンストレーションでしたが、たくさんご質問をいただき、ターボソーミル製材機への関心度の高さをヒシヒシと感じました。
中川町の皆様、ご来場の皆様、どうもありがとうございました!
必要としている方へターボソーミル製材機をお届けできるよう、今後もデモンストレーションを開催していきます!