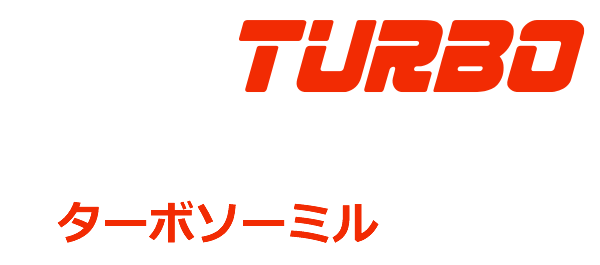「間伐材を有効活用したい」自伐林家向け!簡易製材機で林業に付加価値!

間伐材や未利用材を有効に活用したいと考えている自伐林家さんや少ない設備投資で林業を始めた方にとって、安い丸太にいかに付加価値をつけるかが悩みどころだと思います。
そのお悩みは、どこへでも持ち運べる簡易製材機「turbosawmill(ターボソーミル)」で解決できるかもしれません。
全国で広がる自伐型林業
森林組合や素材生産会社に山の整備を依頼するのではなく、森林所有者が所有する森林や近隣の森林を整備する、自伐型の小さな林業が全国的に注目を集めています。
チェーンソーや軽トラックなど最小限の装備で始めらることや、ノウハウをまとめた書籍も出版されるなど、高価な重機を多数必要とする従来型の林業に比べると参入の障壁は低くなっており、週末に副業的に活動することも可能です。

「先祖が残してくれた山を大事にしたい」
「放置された森林を間伐し、環境をよくしたい」
「地域にたくさん眠っている森林資源を有効活用したい」
など、自伐型林業を始める動機は様々あると思いますが、ほぼすべての人が直面する課題があります。
それは、木の値段が劇的に安いということです。
例えば、スギの立木の値段では、ピーク時の昭和55年には1㎥当たり22,707円でしたが、令和5年には4,361円と約5分の1となっています。
スギ丸太の値段も昭和55年は1㎥当たり39,600円でしたが、令和4年時点では17,600円と半分以下となっています。
ある程度面的なまとまりがある森林を、生産性の高い高性能林業機械等を用いて伐採する素材生産業者であれば、現場を複数こなせば、収益が上がりますが、装備や森林面積が限られる自伐型の林業では、立木を伐採して丸太を販売するだけでは、労働に見合う十分な収益が得られにくいのが現状だと思います。
誰かが決めた価格ではなく、自分で価格を決める
では、どうすればよいでしょうか?
答えは簡単です。
木の値段を高くすればよいのです。
丸太は原木市場での販売や大型製材・合板工場への販売などいくつかの販売方法がありますが、いずれも自分で価格を決めることはできません。
この既存の流通の仕組みに身を任せているうちは、誰かが決めた安い価格で丸太を売ることになりますが、もし自分で丸太から加工品を製造することができれば、自分でその商品に価格を決めて販売することが可能となります。
農業のように野菜をそのまま市場や農協に出荷するのではなく、自ら加工品をつくる6次産業化をするように、林業でもやっちゃおう!ということです。
つまり、柱や外壁、フローリングなどの建築材や家具、木製のおもちゃなどに加工して製品を販売するということです。
ここまで、易々と書いてきましたが、「言うは易し行うは難し」。
手も頭も使うし、大変な行程です。
でも、これをやらないと、自伐的な小さな林業で持続的に稼いでいくのはとても難しいと私たちは考えています。
自分たちで丸太に付加価値を与え、自分たちで価格を決めるのはとても大変な行程ですが、祖父が50年後の孫に託した大切な木を安売りし続けるよりも、健全だと思うのです。
では、具体的にどうすればよいでしょうか?
木材利用の一丁目一番地は製材
丸太を加工するために、必ず必要な行程があります。
それは…
丸太を製材して、角材や板ものなどに加工することです。
しかし、この重要な製材を行う製材所が急激に数を減らしています。
かつては、日本全国どこの農山村でも林業は主要な産業の一つで、各村々に小規模な製材所が稼働し、地域の木を地域で製材して、住宅の構造材や内装材として活用されたり、樽・桶などの商品として利用されていました。
しかし、近年は海外から規格の整った木材が安価に流通するようになったことや、かつては木材だったものがプラスチックなどに代替されるなど生活様式の変化により、国産の木材の需要が減少しています。
また、2000年代に入り、全国的に生産性の高い大規模な製材・合板工場が増加しており、小規模な製材所は減少の一途をたどっています。
実際に私たちの町にはかつて数件の小規模な製材所がありましたが、現在はすべて廃業しており、丸太の販売先が無いだけでなく、賃挽き(丸太を持ち込み代金を支払って、角材や板ものに製材してもらうこと)も頼めない状態です。
遠くの町の製材所に頼る方法もありますが、一度にトラックに載せられる丸太の量は限られ、移動コストがかさんでしまいます。
こうなるとやれることは、自分たちで一丁目一番地をつくるしかありません。
移動式帯鋸製材機を導入。しかし運用に試行錯誤…
そこで私たちは、まずは国内で流通している海外製の移動式製材機を導入することにしました。
導入当初は、初めての製材に興奮して、朝から晩まで製材をしていましたが、ある程度慣れてくると、その生産性に満足できなくなっていました。
というのも、一人で一日に製材できる量が休みなく作業して丸太5~7本程度だったからです。
始めの頃は広葉樹の大径木のストックをテーブル用の一枚板に製材しており、その際はあまり気にならなかったのですが、外壁材やフローリングの需要があり、そのための板を生産しようとしたときに、生産性に限界を感じることが出てきました。
例えば、φ350mm程度のスギ丸太をすべて間柱サイズの板(30㎜×105㎜程度)にしようとすると、休みなく作業して1時間以上必要となり、しかも重い丸太を何度も何度も回転させるので、体力と集中力がすり減っていき、夕方にはヘトヘトの状態という状況です。
しかも、角材の直角(矩)を出すために、架台の調整や丸太の固定を正確にしなければいけないなど、高い技術が必要な場面も多く、体力と集中力が切れかけている夕方には矩がとれていない板を量産するということもざらにありました。
生産性を高める方法もあるのですが、そのためには、製材機とは別に、製材機並みの価格のあれやこれや導入する必要があり、すべてそろえるとかなり大きな金額となるため、導入は見送ることにしました。
理想の製材機を求めてNZへ!誰でも素早く簡単に!簡易製材機Turbosawmill(ターボソーミル)に出会う
あるとき、スマホでインスタのショート動画を眺めている時に、一台の製材機が目に留まりました。
既存の帯鋸式ではなく、丸鋸式で刃が行きと帰りで90度角度を変えて、丸太を一度も回転させることなく、欲しいサイズの板ものや角材をスピーディーに量産しています。
私がこれまで行ってきた丸太を何度も何度も回転させて時間をじっくりかけて行っていた製材がウソのようです。
こうなると現物が見たくなり、恐る恐るアポをとり、2024年初夏にニュージーランドにあるターボソーミル本社に、行くことになりました。




Turbosawmill(ターボソーミル)でできること!
どこへでも運べる製材機
林業の現場では丸太を土場から搬出するために、重機やトラックが必要となります。
週末のみ作業に従事する方や最小限の設備で小さく林業を実施されている自伐林家にとっては、大きいコストを含む課題です。
ターボソーミルは、各パーツごとに分割でき、手動モデルでは軽トラックに載せて容易に持ち運ぶことが可能で、設置も簡単です。
つまり、土場で製材を行うことも可能となります。
製材することで、丸太の価値を数倍~数十倍にできるので、最小限の伐採で収益を向上させることもできるようになります。
例えば、伐倒した丸太の運搬の手段を持たず、仕方なく薪にしていた場合や、軽トラックでしかたどり着けない山深い現場で丸太を搬出できない場合でも、山で製材し、軽くなった製材品を軽トラックで運搬することで、丸太に付加価値をもたらします。
ブレードが往復するだけで誰でも正確に製材
ターボソーミルの最大の特徴は、90度角度を変えるブレードが往復するだけで、正確に直角がとれた角材や板ものを誰でも簡単に素早く生産できるところです。
従来のバンドソーでは角材を生産するためには、製材の都度、丸太を90度回転させる必要があり、多くの労力と時間を要しました。また、正確に直角がとれた角材を生産するためには、架台の調整や丸太の据付、バンドソーの微調整など高い技術が求められました。
また、丸太を載せる架台もないため、丸太の設置も簡単です。
刃のメンテナンスが容易で維持費も安価
ブレードには刃が5枚ついており、研磨に要する時間は1枚あたり10~20秒です。ブレード全体で2分ほどで研磨を終了することができます。
また、研磨に用いるのは市販されている電動ドリルドライバーと、製品に標準で付属されるシャープナーのみで、高価な専用の研磨機を購入する必要はありません。
製材機を持ち出して、新しい林業をスタート!
先に書いたように製材は、木材利用の一丁目一番地です。
製材機を持つことはゴールではありません。ここからが新しい林業のスタートです!
丸太の価値を最大化するために、考えることはたくさんあります。
- どのような寸法の製材するか?
- 製材品をどのように加工するか?
- 誰にどのような価格で販売するか?
- ブランドのロゴはどうするか?
その他にも…
これまで考えたこともなかったようなことをじっくり考えていく必要があります。
自分で価格を決めるということは、大きな苦労を伴います。
思っていた通りにならないことも多々あると思います。
でも、それらを乗り越えて試行錯誤を繰り返し、作り上げた製品やノウハウ、販路は、国内外の大型製材工場で作られる安価な製材品にも負けない力を持っているいるはずです。
さぁ、製材機を持ち出して、新しい林業を始めましょう!

日本では、後発のブランドで新しい機構の製材機となりますが、皆様に信頼していただけるよう、製材のノウハウや具体的な加工方法、ブランディングなど幅広く情報を発信していきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。